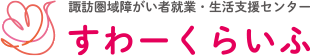一
10月の連休に恒例の登山に行ってきた。趣味というほどではない、年一回、前の職場の同僚三人でヒイヒイ言いながら登る。十年ほど続いているだろうか。
新潟県湯沢町と長野県栄村を隔てる苗場山は2145m。朝から登り夕方に降りてくる日帰り登山としてはぎりぎりの高さかもしれない(登山ガイドには上り4時間、下り3時間とある)。気付かなかったが今改めて地図を見ると昨年登った白砂山(2139m)の隣にある山だ。
二
群馬県みなかみ町の温泉宿に前泊し、翌朝から登る。宿で朝食を取らずに出れば早くから登り始められるのに、宿をいつも朝食付で予約してしまうから登山口に立つのが遅くなってしまう。今回も10時の登山開始で、慣れた人には大丈夫かと心配されてしまう遅い時間だった。秡川(はらいがわ)ルートの登山口1200m付近から標高差900mを登って行く。
苗場山は日本百名山にも指定されている人気の山で、木道がかなり整備されている。その間は数十センチの岩石が無数に集められ踏み固められている。その岩石をヒョイヒョイと登っていくのだが、この岩づたいが帰りに辛くなることの想像はまだできない。これは暗くなったら降(くだ)りが大変だねと言いながら歩く。
一時間半ほど登っただろうか「下の芝」に着く。30分後に中の芝、更に30分後に上の芝と着き、「上」まで来たのだから山頂も近いのかなと感じるが、ここからが長かった。更に30分登って計三時間でようやく高木がなくなり、這い松と山椿、熊笹の高山植物帯に入る。私には名前の判らない小さな白い花が咲いている。
そういえば恐れていた熊に出遭うことはなかった。遭ってしまったら男三人、離れずに闘いながら逃げよう、一人離れると太刀打ちできないから離れないようにしようと話しあっていた。登り始めてすぐに、もう降りてくる人がいて、縦走ルートのない単独峰だから(隣の白砂山には縦走できない)、夜の明ける5時頃から登り始めたのだろう、6時間のピストンで降りてくる健脚家だ。以後30人ほどの人とすれ違っただろうか、これだけ多くの人が登り降りしていて、皆が鈴やラジオを着けているから熊も近寄ってこないのだろうと思われる。鳥以外の動物に遭うことはなかった。
最後の登り一時間がきつい。角度が急になり岩を掴んで登らなければならないところが少なくない。「苗場」――稲の苗を植える湿地の由来になった池塘(ちとう)と呼ばれる小さな沼と水溜まり、湿地帯がこの上に広がっているなどとはとても考えられない山頂が、ガスに包まれてわずかに見える。
三
三時間半が経つ頃から、いわゆるランナーズハイになる。苦しい、きつい、痛いという思いが薄れ、登り歩くこととは違うことを考えるようになる。苦しくなってくると、なぜ自分はこんな思いをしてまで山に登るのだろうかと(人並みに)考える。家族は心配する。でも来年もまた登りたくなるだろうなと思う。すれ違う人に聞くと山頂まで一度降って、その先また登りになるという。「雷清水」という水場に着き、水を十分に飲み水筒に補充する。
14時、登頂。最後の岩場を越えると「天空の楽園」が広がっている(冒頭の写真)。見渡す限りの湿地が広がり、所々に池塘が見える。木道が整備されていて湿地に人の足が入らないようにされている。尾瀬と似た風景だが、ここには登山しなければ来られない(ということを下山しながら考える)。
山頂にあるヒュッテのテーブルに荷物を下ろし、汗で濡れたシャツを脱いで干すなどしながら昼食を取る。先輩がガスバーナーと薬缶を担いできてくれ、同じく同僚が担ぎ上げてくれた二リットルのペットボトルの水を沸かし、私が持って上がったカップラーメン(軽い!)に湯を注ぐ。ホタテ塩ラーメンの塩分が骨にまで滲みるように旨い。ドリップコーヒーは車の中に忘れてしまった。30分ほど休み14時30分に下山を始める。日没は17時20分。それまでにどこまで帰れるか。
四
山頂から一度降ってまた登る。昨年の白砂山も同じだが、登る先に水場があると判っているから力が出る。15時近くになり覆われていたガスが一時晴れてくる。16時、大分降ったはずだがまだ「上の芝」に着かない。日の光が橙色に変わり日没が近い。岩石の上を渡り降る。まだ岩の上に立ってもバランスが取れる。17時、「上の芝」着。17時20分、日没。山あいでもっと早くに日が落ちると思っていたが、思いのほか明るい。ガスが濃くなり、これは霧だ、(山の)下から見れば雲の中だと思う。18時、「中の芝」で少し休む。
歩いていて登山は「修行」だと思う。日本人は何でも「道」にしてしまうと言われるが、修験道(しゅげんどう)の行者は山の中で修業をする。群馬の山には天狗の言い伝えが沢山あり、苗場山の山頂にも役小角(えんのおづぬ)の碑が立っていた。我々も修験道ほどではないが、登山「道」を登り降りする。道――登山道がそのまま修行なのだと気付く。
岩の上に乗せる足が痛い。小指が靴に挟まれて痛みが続く。バランスを崩し、倒れないように踏ん張るのだが、その足の力が出なくなる。乗った木道が滑り尻もちをつく。突いたストックが岩の間に挟まり、先端のゴムが抜けて失くしてしまう。後傾した石の上で踏ん張りがきかず膝をぶつけてしまう。前傾した岩に滑って転ぶ。持っていたストックを振り上げてしまい、危うく後ろを歩く同僚の目に当ててしまいそうになる。辛い降り道が続く。
18時15分、前方に灯りが見える。登山届を出した「和田小屋」の灯りかと思い喜ぶが、すぐに消えてしまう。15分ほど降ると、また灯りが見える。上下に動いているから人の灯りだと気付く。自分たちを捜索しに来たんじゃないかと話すが、違う。中高年の男女二人組(恐らく夫婦で)、どうしましたかと声をかけると、動く気力がなくなってしまい、立ち止まっていたのだと言う。我々が最後だと思います、一緒に歩けますかと訊くと、行きますと答える。あと30分で和田小屋ですと告げると、ゆっくりと歩き始めることができる。
18時45分、和田小屋着。深い霧の中、水で手を洗い喉を潤しベンチに座って休む。夫婦はここまで来れば大丈夫だと言う。会えて良かったと言いあって別れる。登山口まで30分、舗装された道を歩く。足は痛むが、やっと終わると思う。19時15分、下山。宿に電話をして20時着と伝える。食事を温めておいてくれると言われ感謝する。